ページ内リンク
真空試験P163~P164
【真空試験】の問題と次頁の【試運転】は一気に攻略してしまいたい。
『初級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<8次:P163~P164 (13.4 真空試験(真空放置試験))> テキストに沿って(1)~(8)の該当問題を並べてあります。
・圧縮機など配管以外の部分について耐圧強度を確認してからそれらを配管で接続して、すべての冷媒系統について必ず真空試験を行ってから気密試験を行う。 H24/13 
【×】 平成24年度(><;)気密試験の復習を込めてココに置く。
配管以外の部分について耐圧強度…云々は、正しい。<8次:P161 (13.2 耐圧試験)>(2)です。
すべての冷媒系統について(←これ、わりと重要)は、正しい。<8次:P161 (13.2 耐圧試験)>の冒頭2行目。
正しい文章は、
圧縮機など配管以外の部分について耐圧強度を確認してからそれらを配管で接続して、すべての冷媒系統について必ず気密試験を行ってから真空試験を行う。
(1)(2) 真空度とポンプP163,P164
8次改訂版での真空試験(圧力)真空度について
『初級 冷凍受験テキスト(令和元年11月30日:8次改訂版)』と『『初級 冷凍受験テキスト(令和3年10月11日:8次改訂第5刷)』で、163ページ最下行の表記内容が違っています。(空調学会webサイトの「正誤表」に掲載されてます。)
「令和元年11月30日:8次改訂版」では、
(1) 到達真空度は、少なくとも-93 kPa(絶対圧力では8 kPa)程度で行う.
「令和3年10月11日:8次改訂第5刷」では、
(1) 真空試験の圧力は0.6 kPa (5 torr)以下の真空度で行う.
出版元に問い合わせしたところ、令和3年3月31日発行の第3刷発行時に変更したそうです。理由は、真空度がバラバラだったのを一般社団法人日本冷凍空調工業会に基準を合わせたとのことです。((2021(R03)/11/11記ス))
真空試験圧力の具体的数値の出題は、平成21問13で出題されています。今後どうなるかわかりませんが、今年(令和3年度(2021年)の11月14日試験では出題されないと思われます。(2021(R03)/11/──)
・冷凍装置の真空放置試験を、内圧8 kPa(絶対圧力)で実施した。 H21/13 
【◯】 具体的な数値がでたのはこの年度が初めてかな。でもテキストには一番先の項目にある。ま、覚えよう。テキスト<8次:P163 (1)>
・冷凍装置の真空放置試験を、内圧0.6 kpa(5 torr)以下の真空度で実施した。 by echo 
【◯】 世は移り変わり令和になった昨今の装置は精密化が進み、「日本冷凍空調工業会」試験真空度の基準も変化しているようです。
torr(トル)とは
(5 torr)(「5トル」と読む)とさり気なく記されているが、なんぞや?という感じである。
Wikipedia 「トル」 より引用
トル(torr、記号: Torr)は、圧力の単位である。メートル法に基づく単位であるが、SI単位ではない。
トルは日本の計量法体系においては、特殊の計量である「生体内の圧力の計量」に限って使用することができる。正確に101325/760Paと定義されている。これは標準大気圧の1⁄760という意味である。約133.322 Paである。
というわけで、冷凍設備に「生体内の圧力の計量」が関係するのだろうか??SI単位ではないというし…、よくわかりませぬ。
5 torr = 5 × 133.322 Pa = 666.61 pa ≒ 0.67 kpa
ということで、ま、「0.6 kpa(5 torr)」と記されているのでしょう。
・真空放置試験を実施する場合には、圧縮機軸受が過熱しないように注意して行えば、冷凍装置の圧縮機を用いて実施してもよい。 H18/13 
【×】 だめ!なんとなく、わかっちゃう問題。これは、サービス問題かな。真空ポンプで行う。テキスト<8次:P164 (2)>
(3) 真空計P164
圧力計・真空計・連成計の概略図を掲載します。
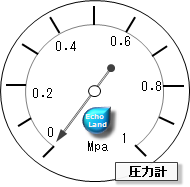
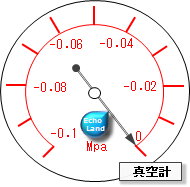
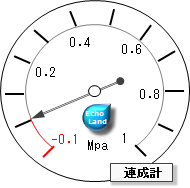
・真空乾燥を行うときは、連成計を用いて圧力を測定し、真空状態を数時間以上保つことが必要である。 H11/13 
【×】 連成計ではなく真空計を用い、設備の大きさ構造により数時間から一昼夜近い時間で内部に残留水分がないように十分に乾燥させる。テキスト<8次:P164 (3)(7)>
・真空試験(真空放置試験)では、真空圧力の測定には連成計が用いられる。 H20/13 
【×】 「連成計」の問題は、忘れたころに出題されるんですね。ここで4問攻略したあなたは当分?大丈夫。(2012(H24)/06/03記ス)
(4)(5) 目的P164
【参考/真空試験】 真空放置試験(真空試験)は、法には定められていないが、水分を嫌うフルオロカーボン冷凍装置や冷凍設備内の微量の漏れの発見のために気密試験の後に行う。
・真空試験は、気密試験と同様に微少な漏えい箇所を発見するために行う。 H23/13 
【×】 引っかからないように。
どこかで漏れがあるとわかっても、漏洩箇所の発見はできない。 テキスト<8次:P164 (4)>
・真空試験は、冷凍装置の最終確認として微少な漏れ箇所の特定のために行う。 H27/13
・徴量の漏れを嫌うフルオロカーボン冷凍装置の真空試験は、徴量の漏れや漏れの箇所を特定することができる。 H30/13 
【両方 ×】 ぅむ。漏れ箇所の特定はできませぬ。テキスト<8次:P164 (4)>
・冷凍装置全体の気密試験を行った後に、装置の気密の最終確認をするために真空放置試験を実施した。 H18/13 
【◯】 真空試験は、気密試験後の気密(漏れ)最終確認です。テキスト<8次:P164 (5)>
(6)(7)(8) 方法P164
(6)~(8)を分類し、年代順に並べます。
(6)
(7)
(8)
・真空放置試験では、冷凍装置内部の乾燥のため、必要に応じて水分の残留しやすい場所を加熱するとよい。 H19/13 
【◯】 無勉だと惑わされる問題。その場所を中心に120度以下で加熱してあげるとよい。テキスト<8次:P164 (8)>
・真空試験では、装置内に残留水分があると真空になりにくいので、乾燥のために水分の残留しやすい場所を、120℃を超えない範囲で加熱するとよい。 R01/13 
【◯】 ついに「120℃」が出ました。設問では 120度を超えない範囲
とありますが、テキスト<8次:P164 (8)>では 120℃以下
と、なっています。今後、 120℃以上
とか 120℃程度
とか、惑わされるのかな?
03/04/21 04/09/05 05/03/21 07/03/24 08/03/15 08/04/26 09/05/31 10/09/12 12/06/03 13/06/06 14/08/12 15/06/23 17/02/14 19/08/02 20/07/06 21/11/11 22/01/21 23/11/30 24/11/22 25/12/09
『初級 冷凍受験テキスト』8次改訂版への見直し、済。(22/01/19)
修正・訂正箇所履歴
【2016/06/11 新設】
- 挿絵を挿入および文章見直し。(2019(R1)/08/02)
- テキスト8次改訂版(R01(2019)-11月改訂)へ対応、および、文章を見直し。(2020(R02)/07/06)
- 補足として「8次改訂版での真空試験圧力につい」を追加。(2021(R03)/11/11)
- 問題の分類見直し、および予想問題追加。(2022(R04)/01/21)
- (6)~(8)を分類。(2023(R05)/11/30)
-- コラム --
【参考文献】
- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会
- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会
- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会
- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院
- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院