ページ内リンク
構造と伝熱(1) P86~P88(P86~P88)
「学識」問5で出題される、水冷凝縮器の「横型シェルアンドチューブ凝縮器」「二重管凝縮器」「ブレージングプレート凝縮器」を集めてあります。テキストは<9次:P86~P88>(P86~P88)です。
各々の凝縮器の、「管内」「管外」に、なにが流れているのか整理しましょう。
テキスト9次改訂版について
『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。
横型シェルアンドチューブ凝縮器 P86~P87(P86~P87)
図は、シェルアンドチューブ凝縮器断面図の概略図である。シェル(円筒胴)の中に、冷却水が通るチューブ(管)が配置されている。テキストでは<9次:P87 上>に詳細図が記されている。一度ジックリ見て読んでイメージを膨らませてほしい。
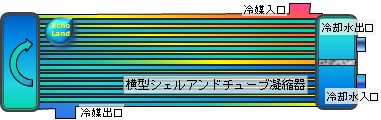
横形シェルアンドチューブ凝縮器の概略図
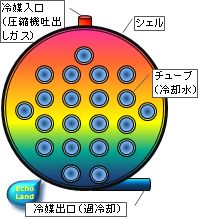
横形シェルアンドチューブ凝縮器(断面図)概略図
- 上部より圧縮機吐出しガスが入ると、冷却管で冷却され外表面に凝縮し、液滴となって落下し下部に冷媒液が溜まる。
- 最下部の冷却管が液に浸され、過冷却を図るとともに、受液器の役目も持たせる場合がある。コンデンサ・レシーバ(受液器兼用水冷凝縮器)
テキストでは、このシェルアンドチューブ凝縮器が水冷凝縮器の中心となって進んでいきます。
・水冷シェルアンドチューブ凝縮器は、冷却管内を冷却水が流れ、管外面で冷媒蒸気が凝縮する。 H17学/05 
【◯】 ぅむ。「冷却管内を冷却水、管外面で冷媒蒸気」これは暗記。テキスト<9次:P86右下~P87左上>
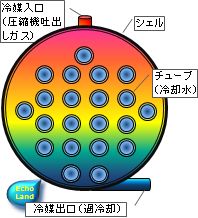
横形シェルアンドチューブ凝縮器(断面図)概略図
・横型シェルアンドチューブ凝縮器は、横置きされた鋼板製の円筒胴内に多数の冷却管を配置したもので、冷却管はその両端を鋼製管板に拡管して圧着されている。冷却水は冷却管の外側を流れる。 H21学/05 
【×】 むむ、冷却水は冷却管の内側です。冷媒が外側。テキスト<9次:P86右下>
「拡管」というのは、管を拡げる(広げる)ということと思われる。空冷凝縮器の説明ですが<9次:P83の左下あたり>を読み図7.4を見れば分かるでしょう。頑張れー。
・水冷横形シェルアンドチューブ凝縮器は、横置きされた鋼板製の円筒胴内に多数の冷却管を配置したもので、一般的には冷却管はその両端を鋼製管板に拡管して圧着される。水室カバーは取り外し可能な構造になっている。 H27学/05 
【◯】 ぅむ。テキスト<9次:P86右~P87左>をうまくまとめた感じでつね。よく読んでイメージしておくしかないでしょう。
二重管凝縮器 P87~P88(P87)
二重管は忘れた頃に出題される。
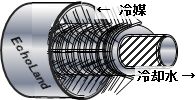
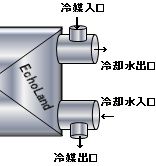
・水冷凝縮器として使用されている二重管凝縮器は、同心の二重管よりなり、一般的に冷媒蒸気は二つの管の隙間を上から下へ向かって流れ、冷却水は内側の冷却管内を下から上へ向かって流れる。 H28学/05 
【◯】 ぅむ。
・二重管凝縮器は、同心の二重管よりなり、一般に、冷媒蒸気は二重管の隙間を流れ、冷却水は内側の冷却管内を冷媒の流れ方向と逆向きに流れる。 R01学/05 
【◯】 その通り。テキスト<9次:P87 図7.12>を参照のこと。
・ 二重管凝縮器は、冷媒流れ抵抗により長さが制限されるため、容量を増やすには並列につなぐ必要があり配管が複雑になるため、小容量のものに使用されている。by echo 
【◯】 たしかに見た目で、そう感じますね。テキスト<9次:P88左上の3行>
・二重管凝縮器は、構造上、シェルアンドチューブ凝縮器に見られる管板は不要であるが、冷媒側の流れ抵抗によりその長さが制限される。そのため、熱交換容量を増やそうとすると、複数の二重管を並列に配置して使用する必要があり、配管が複雑になることから、もっぱら小形の冷凍装置に使用される。 R07学/05 
【◯】 テキスト<9次:P87右下~P88左上の3行>を上手にまとめた問題文です。👍️
ブレージングプレート凝縮器 P88(P90)
このブレージングプレート凝縮器は、H23(2011)年12月の7次改訂版から、追加された。テキスト<9次:P88>(P90)
・ブレージングプレート凝縮器の伝熱プレートは、銅製の伝熱プレートを多層に積層し、それらを圧着して一体化し強度と気密性を確保している。
H26学/05 H30学/05( 一体化し、強度と
句読点があるだけ)
【×】 間違いは2つ。正しい文章にしておきましょう。テキスト<9次:P88左>
ブレージングプレート凝縮器の伝熱プレートは、ステンレス製の伝熱プレートを多層に積層し、それらをろう付け(ブレージング)して一体化し強度と気密性を確保している。
今後、このブレージングプレート凝縮器は結構出題されるかもしれません。熟読してください。
・プレージングプレート凝縮器は、一般的に小形高性能であり、冷媒充てん量が少なくてすみ、冷却水側のスケール付着や詰まりに強いという利点がある。 H28学/05 
【×】 冷却水側のスケール付着や詰まりしやすい感じがしますよね!?テキストは<9次:P88右上> 正しい文章にしておきましょう。
プレージングプレート凝縮器は、一般的に小形高性能であり、冷媒充てん量が少なくてすむ。しかし、冷却水側のスケール付着や詰まりに注意する必要がある。
・ブレージングプレート凝縮器は、板状のステンレス製伝熱プレートを多数積層し、これらを、ろう付けによって密封した熱交換器である。この凝縮器は、小形高性能であり、冷媒充てん量が少なくて済むことなどが特徴である。 R02学/05 
【◯】 上記2つの問題文章を上手にまとめた良い日本語の問題です。テキスト<9次:P88>
・ブレージングプレート凝縮器は、一般に、小形高性能であり、冷凍装置への冷媒充填量が少なくてすみ、冷却水側のスケール付着や詰まりに注意する必要がない。 R06学/05 
【×】 H28と同等だが別にした。正しい文章は、
「ブレージングプレート凝縮器は、一般に、小形高性能であり、冷凍装置への冷媒充填量が少なくてすむ。しかし、冷却水側のスケール付着や詰まりに注意する必要がある。」
05/10/01 07/12/12 08/02/03 09/03/20 10/09/28 11/08/01 12/04/16 13/10/09 14/09/13 15/07/20 16/12/02 17/12/30 19/12/14 20/11/26 22/04/06 23/05/15
-- コラム --
修正・訂正箇所履歴
【2016/06/29 新設】(← 履歴をここに作った日)
- テキスト8次改訂版へ対応。解説も少々見直し済み。(2016(H28)/12/02)
- 「構造」内の問題で「保安」で出題された「凝縮圧力の上昇」の問題は、新規ページ「水冷凝縮器(凝縮圧力異常上昇)」作成し移動した。
- 二重管凝縮器を、1ブロックにまとめた。(2017/03/10)
- 「学識」問7(熱交換器・運転状態)一部の問題は、「熱交換器」ページへお引っ越し。(2017/03/12)
- 問題分類と解説を少々見直し。(2019(R1)/06/02)
- 図を追加、及び解説見直し。(2019(R1)/09/14)
- 図を追加、及び解説見直し。(2019(R1)/12/14)
- 分類など、全体的に見直し。(2022(R04)/04/05)
- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応(23(R05)/04/07)
- 「ブレージングプレート凝縮器」を「構造と伝熱(2)」より移動追加。(23(R05)/05/15)
【参考文献・リンク】
- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会
- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会
- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会
- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院
- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院