ページ内リンク
湿り運転の原因とその影響と対応、運転停止 P204~205(P196~197)
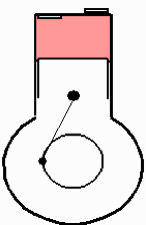
湿り運転は、液圧縮などによる圧力上昇や弁破壊につながるため、問題数は それなり
です。
テキスト9次改訂版について
『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。
湿り運転の原因 P204(P196)
・圧縮機の停止中、クランクケース内の油温が高いと、始動時にオイルフォーミングを発生することがある。(R22往復圧縮機) H13保/01 
【×】 油温が低いとフロン冷媒は油に溶けやすく始動時にオイルフォーミングを起こす。なので、オイルヒーターで温めている、点検時は必ず油温をチェックする。
テキス<9次:P204右(e)>あたりと、<9次:P207「油ヒータ」>を読むべし。
・圧縮機停止中のクランクケース温度が高かった。(圧縮機が湿り運転になる原因) H15保/01 
【×】 停止中はわざわざヒーターで温めている。クランクケース内の油温が低いと冷媒が溶け込んで、オイルフォーミングが発生する。テキスト<9次:P204右(e)>、<9次:P207「油ヒータ」>
・吸込み配管の途中に大きなトラップがあり、装置の運転停止中にトラップに凝縮した冷媒液や油が溜まっていると、圧縮機始動時に液戻りが生じることがある。 H25保/01

【◯】 「配管」で出題されそうな問題であるが、ここ湿り運転にも記される。 テキスト<9次:P204左(b)>
・圧縮機運転中、温度自動膨張弁の感温筒が吸込み管から外れて、感温筒の温度が上昇すると、膨張弁が開き過ぎになって、過剰な冷媒液が蒸発器に流入して液戻りが起きる。 H26保/01 
【◯】 テキスト<9次:P204(c)>にズバリ。
・圧縮機運転中、温度自動膨張弁の感温筒が吸込み蒸気配管から外れて、感温筒の温度が上昇すると、膨張弁が閉じて、圧縮機が過熱運転となる。 H29保/01 
【×】 正しい文章にしてみましょう。
圧縮機運転中、温度自動膨張弁の感温筒が吸込み蒸気配管から外れて、感温筒の温度が上昇すると、膨張弁が開き過ぎになって、圧縮機が湿り運転となる。
テキスト<9次:P204(c)>全く逆の動作と影響の問題文です。
・圧縮機運転中、温度自動膨張弁の感温筒が吸込み蒸気配管からはずれて感温筒の温度が上昇すると、膨張弁の開度が低下し、冷媒循環量が減少する。 H30保/01 
【×】 上記「H26保/01」の問題文を【×】に改良したもの。 テキスト<9次:P204(c)>
圧縮機運転中、温度自動膨張弁の感温筒が吸込み蒸気配管からはずれて感温筒の温度が上昇すると、膨張弁の開度が開き過ぎになって、冷媒循環量が過剰に増加する。
・圧縮機が、アンロード運転からフルロード運転に切り換わった際、圧縮機容量が増加して吸込み蒸気圧力が上昇し、液戻りが起きて液圧縮になることがある。 R01保/01
R06保/01(「、」の有無の違いのみ。) 
【×】 テキスト<9次:P204左(a)>です。正しい文章は、
「圧縮機が、アンロード運転からフルロード運転に切り換わった際、圧縮機容量が増加して吸込み蒸気圧力が低下し、液戻りが起きて液圧縮になることがある。」
・圧縮機が、アンロード運転からフルロード運転になると、圧縮機容量が急増して吸込み蒸気圧力が急激に上昇し、液戻りが起きて液圧縮になることがある。 R05保/01 
【×】 上記問題と同等。「急増」「急激」が追加されている。(テキスト通り)
「圧縮機が、アンロード運転からフルロード運転になると、圧縮機容量が急増して吸込み蒸気圧力が急激に低下し、液戻りが起きて液圧縮になることがある。」
・圧縮機の湿り圧縮や液戻りの原因としては、冷凍負荷の急激な変化、吸込み蒸気配管の途中に設けた大きなトラップ、温度自動膨張弁の感温筒が吸込み蒸気配管から外れることなどがある。 R04保/01 
【◯】 テキスト<9次:P204 (a)(b)(c)> (a)(b)(c)を、綺麗に(?)まとめた問題文。
湿り運転の影響(オイルフォーミング)と対応 P204~205(P196~197)
・圧縮機に液戻りが起きると、オイルフォーミングが発生するが、潤滑不良を起こすことはない。 H18保/01 
【×】 冷媒液が急激に沸騰しオイルフォーミングが起こり、潤滑不良になり油ポンプの油圧が低下し、潤滑不良になる。テキスト<9次:P204右下~P205左上>を読む。
・圧縮機が湿り蒸気を吸込むと、圧縮機の吐出しガスの温度が低下し、オイルフォーミングを発生することがある。(往復圧縮機) H21保/01 
【◯】 テキスト<9次:P204~P205「湿り運転の影響と対応」>をジックリ読むべし。
・圧縮機が湿り蒸気を吸い込むと、吐出しガス温度が低下する。この運転状態が続き、圧縮機が液戻りの状態になっても、油圧保護圧力スイッチが作動することはなく、圧縮機は停止しない。 H22保/01 
【×】 液戻りが起こると、冷媒液が急激に沸騰しオイルフォーミングが起こり、潤滑不良になり油ポンプの油圧が低下し、油圧保護圧力スイッチが作動し圧縮機を停止させる。
テキスト<8次:P205左上>をよく読もう。
・多気筒圧縮機が湿り蒸気を吸い込むと、吐出しガス温度が低下する。この運転状態が続き、液戻りの状態が続いても、一般に、油圧保護圧力スイッチが作動することはなく、圧縮機は停止しない。 R02保/01 
【×】 10年前の「H22保/01」の問題文と微妙に変わっているところをお楽しみください。<解説略>
・フルオロカーボンを冷媒とする圧縮機では、運転停止中のクランクケース内の油温が低いと多量の冷媒が油に溶解し、始動時に、オイルフォーミングの発生によって液圧縮を起こして、潤滑不良や弁割れを起こすことがある。 H30保/01 
【◯】 テキスト<9次:P205左上>辺りを読むしかない。
【参考】 弁割れ
という語句はテキストにはなくて、 吐出し弁や吸込み弁を破壊し
とある。
運転停止 P205(P197)
「(1)短時間の停止」と「(2)長期間の停止」の内容を整理しておきましょう。出題数は少ないです。
(1)短時間の停止
・圧縮機を手動で操作して停止させる場合、受液器液出口弁を閉じてしばらく運転し、受液器に冷媒液を回収する必要がある。これは、液封の防止などのために必要な措置である。 R03保/01
R03保/01(「回収しておく。これは、」、他同じ。) 
【◯】 他に、蒸発器に滞留した冷媒液による始動時の液戻り防止もある。テキスト<9次:P205左下(a)>
・停止中には、油分離器からの返油弁を閉じ、油分離器で凝縮した冷媒液が、圧縮機に戻るのを防止するが、短時間の停止なら必要ない。 by echo 
【×】 短時間でも返油弁を閉じなければなりません。テキスト<8次:P197左下(C)>
(1)長期間の停止
・長期間停止の場合、低圧側の冷媒液を受液器に回収し、バルブは後側のみ閉めておく。なお、装置への空気侵入防止のためゲージ圧力0.01Mpa程度のガス圧を残しておく必要がある。 by echo 
【×】 受液器の前後のバルブは閉じておく。ガス圧云々は正解。テキスト<8次:P197右(a)>
・圧縮機を長期にわたって停止し凍結のおそれのある場合、凝縮器、潤滑油冷却器の冷却水は排水するが、圧縮機シリンダのウオータジャケットの冷却水の排水は必要ない。
H25保/01 
【×】 テキスト<9次:P205右(c)>
ウォータージャケットがなんだかわからない場合は、ネットで画像検索 → Google画像検索結果
20/11/20 22/02/26 23/12/06 24/11/28
-- コラム --
修正・訂正箇所履歴
【2020(R02)/01/02 新設】(← 履歴をここに作った日)
- ページ分割、及び、文章見直し(2020(R02)/09/08)
- 予想問題 by echoを追加。(2022(R04)/02/26)
- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応(23(R05)/04/07)
- 問題の選択、文章見直し(23(R05)/04/07)
【参考文献・リンク】
- 初級受検テキスト:日本冷凍空調学会
- 上級受検テキスト(上級受検テキスト):日本冷凍空調学会
- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例:日本冷凍空調学会
- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院
- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院